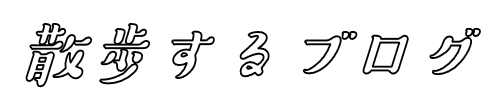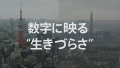■ 42.195kmという「中途半端な数字」の理由
マラソンの距離はなぜ42.195kmなのか――。
じつは、これには歴史的な経緯があります。
1908年のロンドンオリンピックで、スタート地点をウィンザー城、ゴールを競技場の貴賓席前に設定したところ、距離が偶然42.195kmになりました。
この数字がその後の大会でも採用され、1921年に正式に国際陸上競技連盟(現World Athletics)が「マラソンは42.195km」と定めたのです。
いまでは世界中のマラソンがこの距離で統一されています。
■ 意外にも「自転車」で測っている
現代ではGPSやレーザー距離計などの最新技術があるのに、マラソンの距離測定は今でも自転車で行われています。
使用されるのは「ジョーンズカウンター(Jones Counter)」という精密な機械で、自転車の前輪に取り付けて回転数をカウントします。
1回転あたりの回数を基準にして、走行した距離を正確に算出する仕組みです。
この装置の特徴は「単純だけど極めて安定」なことです。
GPSのように電波状況や衛星の誤差に影響されず、数センチ単位の精度で測ることができます。
実際、ジョーンズカウンターによる測定誤差は1万分の1以下といわれています。
現代ではGPSやレーザー距離計などの最新技術があるのに、マラソンの距離測定は今でも自転車で行われています。
使用されるのは「ジョーンズカウンター(Jones Counter)」という精密な機械で、自転車の前輪に取り付けて回転数をカウントします。
1回転あたりの回数を基準にして、走行した距離を正確に算出する仕組みです。

■ 校正(キャリブレーション)でミリ単位の誤差を補正
計測の前後では必ず「校正(キャリブレーション)」が行われます。
たとえば、1kmの直線道路を測量機器であらかじめ正確に測っておき、その区間を自転車で走って回転数を記録します。
これにより、「1回転=〇メートル」という換算値を算出します。
さらに、計測後にも同じ区間を走り、前後の誤差を確認して補正します。
これによって、温度やタイヤ空気圧の変化、路面の摩擦などによるズレが平均化され、極めて正確な距離を導き出すことができるのです。
■ 実際の測定はどう行われているのか
マラソンコースの測定は、大会の数週間から数か月前に行われます。
深夜や早朝の交通量が少ない時間帯に、警察や自治体の許可を得て公道を一時的に通行止めにします。
測定チームは2〜4人ほどで構成され、先導車が安全を確保しながら、測定員が自転車でコースを走ります。
走行するラインは「最短走行ライン(Shortest Possible Route)」と呼ばれ、選手が実際に走れる最も短いルートを通るのがルールです。
たとえば、カーブではイン側をギリギリまで攻め、直線では道路の端をまっすぐ進みます。
これにより、選手が理論上最短で走った場合の距離が42.195kmになるように測定されるのです。
■ よれ(蛇行)はどうやって補正しているのか?
「人が自転車で走るなら、よれてしまうこともあるのでは?」
そう思う方も多いでしょう。
実際、多少の蛇行(スネーキング)は起こりますが、それを校正とデータ検証で完全に補正しています。
まず、前後の校正走行でタイヤの回転係数を正確に算出します。
これによって、走行中のよれや空気圧変化なども「平均的な補正値」として吸収できます。
さらに、測定は必ず2人以上の公認測定員が別々に走り、それぞれのデータを比較します。
もし2人の結果に20メートル以上の差があれば、その区間を再測定します。
これによって、人間のよれを科学的に消し込むことができるのです。
また、国際ルールでは「Short Course Prevention Factor(短縮防止係数)」として、測定距離に0.1%の余裕を加える決まりがあります。
つまり、実際には42.195kmではなく、42.237kmほど測定されています。
少し長めにしておくことで、万が一の誤差を完全に防ぐのです。
■ 測定員は「資格を持つプロ」
マラソンコースの測定を行うのは、特別な資格を持った専門家です。
日本では日本陸上競技連盟(JAAF)が認定する「公認測定員」が担当します。
測定員は特別な講習と実技試験を経て認定され、国際マラソン協会(AIMS)の基準に従って測定します。
測定が終わると、距離データ・コース図・標識位置・キャリブレーションシートなどをまとめた報告書を提出し、
AIMSと陸連の審査を経て初めて「公認コース」として登録されます。
この手続きを経ない限り、世界記録や大会記録は公式には認定されません。
■ 一度測ったらずっと使えるのか?
コースは一度認定されればしばらく有効ですが、永遠ではありません。
道路は日々変化しています。
車線の拡幅、歩道の整備、信号機の新設など、わずかな変更でもルートの最短ラインが変わるため、再測定が必要になります。
東京マラソンを例にすると、2007年の初開催以来、再開発や五輪関連工事により何度も再測定が行われています。
スタート地点やゴール地点の位置には「金属ピン」や「白線」で永久標識が打たれ、次回以降の測定にも使えるようになっています。
■ GPSではだめなのか?
スマートウォッチやスマホのGPSは便利ですが、数メートル単位の誤差が出ます。
ビル街や高架下では電波が反射し、実際よりも長く表示されることもあります。
そのため、公式な距離測定には使えません。
ただし最近では、ジョーンズカウンターによるデータに加えて、GPSログも「補助的な検証手段」として使われています。
走行ルートを可視化して、コーナーの膨らみやラインのズレをチェックするのです。
つまり、アナログとデジタルの融合によって、より高い信頼性が確保されています。
■ それほど厳密に測る理由
マラソンは陸上競技の中で唯一、公道を使う競技です。
スタジアムのトラックとは違い、毎回のコースが異なるため、
正確に42.195kmを測らないと世界記録の比較ができなくなってしまいます。
わずか10メートルの誤差でも記録に数秒の差が出ることがあります。
そのため、距離測定は単なる事務作業ではなく、競技の公平性を守るための職人仕事なのです。
■ まとめ:アナログだからこそ信頼される世界
夜明け前の静かな街で、先導車の後ろをヘルメット姿の測定員が自転車で進みます。
聞こえるのは、ジョーンズカウンターの小さな「カチ、カチ」という音だけ。
42.195kmという数字の裏には、こうした地味で緻密な作業があります。
最新技術の時代にあっても、最も正確に距離を測る方法は「人間の手と自転車」。
マラソンのコースには、ランナーだけでなく、
目に見えない「測定のプロたちの情熱」も刻まれているのです。