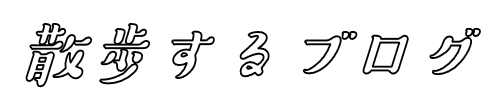「今、少数与党となっているが、現状が一番よいように感じる。多政党もいいことだと思う。どうしても、自民一党だと、結局自民が決めればそれで決まっちゃう感覚がある。そうなると国民は政治に対して関心を持てなくなる。今の状態だと、自分が応援したい政党に投票しようという気持ちになる。たとえ結果がどうであれ。一党支配だとお金にもルーズになってくるし、お山の大将的な政治家が出てきやすくなる。」
――この言葉には、いまの日本の政治状況を見つめる多くの国民の実感が込められている。
混乱や不安定さよりもむしろ、「政治が国民の手に少し戻ってきた」という希望を感じている人は少なくないだろう。
■ 一強の影に潜んでいた“麻痺”
戦後日本の政治は、長らく自民党を中心に回ってきた。
安定した政権運営、経済成長の基盤づくり、防衛・外交の継続性――これらの功績を否定することはできない。
しかし一方で、あまりに長く続いた一強体制は、「決められる政治」を超えて、「決まってしまう政治」へと変質していった。
国会での議論は形式化し、党内での派閥均衡や忖度が優先される。
野党の提案は届かず、メディアの追及も次第に熱を失っていく。
気がつけば国民の多くが、「どうせ変わらない」「誰がやっても同じ」と思うようになった。
それこそが、民主主義にとって最も危うい“思考停止”の状態である。
政治が「一強の手の中」で完結してしまうと、権力を監視する目が鈍る。
結果として、不透明なお金の流れや不正への感覚が麻痺する。
政治家が「選ばれた人」ではなく「選ばれ続ける人」になるとき、そこに緊張感は消える。
■ 少数与党がもたらした“風通し”
近年、与党が過半数を割るか、あるいは維持できても辛うじて、という国会構成が続いている。
この状況を「不安定」と見る声もあるが、視点を変えれば、むしろ“健全な揺らぎ”だ。
政策一つを通すにも、与野党の調整が必要になる。
野党の意見にも耳を傾けざるを得ない。
メディアも再び国会論戦を報じるようになり、政治が「見える場所」に戻ってきた。
かつてのように、閣議決定ですべてが一瞬で決まるということは減った。
議論が増え、法案が通るまで時間がかかることもある。
だが、それは「混乱」ではなく、「熟議」だ。
少数与党の時代にこそ、政治は本来の形を取り戻す。
人々が「この党に任せたい」「この政策を支持したい」と思い、投票行動に移す。
結果がどうであれ、そのプロセスに参加しているという実感は、国民の政治意識を確実に変えていく。
■ 多党制は“面倒”だが、だからこそ価値がある
多党制のもとでは、意見が割れ、政策決定までの道のりが長くなる。
「スピード感がない」と批判されることも多い。
だが、それは“面倒”な民主主義の宿命であると同時に、その価値そのものでもある。
民主主義とは、異なる立場の人々が話し合い、妥協し、折り合いをつけていく制度だ。
たとえ時間がかかっても、少数の声が切り捨てられないということが重要なのだ。
ドイツや北欧諸国のように、複数政党が連立を組んで国を運営している例は多い。
そこでは、「安定」と「対話」が同時に存在する。
リーダーが代わっても、政策の方向性が極端に揺れず、政治全体が一つの文化として成熟していく。
日本も、いまようやくその段階に足を踏み入れつつあるのではないか。
時間をかけて対話を重ねることを「遅い」と笑うのではなく、
その過程を「民主主義の筋トレ」として誇れる国になること。
それが、これからの日本政治の理想形だ。
■ “無関心”から“多様な関心”へ
一強時代の最大の副作用は、国民の「無関心」だった。
どんな政策が通ろうと、どんな不祥事があろうと、政権は揺るがない――。
そう思った瞬間に、政治は「遠い世界」の出来事になる。
だが、政権が揺らぐ今、人々は再び“見る目”を取り戻し始めている。
SNSやネットニュースでは、法案審議や記者会見の様子がリアルタイムで共有される。
「この政策は賛成」「あの発言はおかしい」と、誰もが自分の意見を発信できるようになった。
たとえ拙くても、その声が社会を動かすきっかけになる。
「推し政党」や「推し議員」という言葉が登場したのも、ある意味で健全だ。
それは、政治を再び“文化”として語れる社会への兆しだ。
投票率が上がるよりも前に、まず関心が戻ってきたことが重要である。
■ 政治が「国民の手に」戻るということ
民主主義における“理想の政権”とは、単に安定している政権ではない。
常に国民の目と声にさらされ、批判や意見を受け止める柔軟な政権である。
多数派であっても独善に陥らず、少数派であっても責任を放棄しない。
そんな政治の姿勢こそが、社会の信頼を支える。
少数与党の現状は、その意味で試練であり、チャンスでもある。
与党は「協力を得る力」を、野党は「提案する力」を磨かねばならない。
国民は「見守るだけでなく、参加する責任」を持つ。
政治を“任せる”のではなく、“一緒に進める”時代が始まっている。
■ 終章:いま、民主主義は呼吸している
かつて日本の政治は「安定」を理由に、長く一強に支えられてきた。
だが、その安定が国民の無力感と引き換えだったのなら、それはもう必要ない。
少数与党という現実は、見方を変えれば「民主主義が再び呼吸を始めた証」なのだ。
決まらない政治を嘆くのではなく、決まるまでの議論を誇りたい。
時間がかかる政治を批判するのではなく、その遅さの中に誠実さを見出したい。
そして何より――
「政治が、国民の手に少し戻ってきた。」
そう感じられる今こそ、私たちがもう一度、民主主義を信じ直す時ではないだろうか。