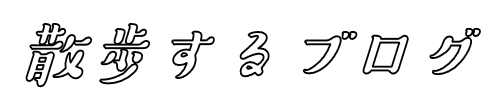■ 序章:クマが“毎日のニュース”になった日本社会
2023年から2025年にかけて、日本ではクマに関するニュースがほぼ連日のように報じられるようになった。
「住宅街にクマ」「通学路に出没」「畑で襲われる」「駆除か保護かで議論」。
これらは単なる“地方の野生動物ニュース”ではなく、日本の安全保障、環境問題、そして社会観まで巻き込む大きなテーマとなりつつある。
ヒグマ・ツキノワグマは本来、深い森の奥で人間を避けて生きる動物だ。
しかし近年、人里や都市近くまで姿を見せるケースが急増している。
その背景には、個体数増加、里山の変化、人口減少、気候変動、そして“人と自然の距離”の変化が複雑に絡み合っている。
一方で、「自然破壊を続けてきたのは人間の側だ」という意見もある。
動物愛護の観点から「安易な駆除はすべきではない」と考える人も多い。
しかし現実には、毎年のように人命が奪われ、農林業被害は深刻化し、観光地の安全性や子供の登下校にも影響が出ている。
では、日本はこれからクマとどう向き合えばよいのか。
そして、世界の国々は同じ問題にどう向き合ってきたのか。
■ 日本のクマはなぜ増え、人里に現れるようになったのか
日本のクマ問題を語るには、まず「なぜ今こんなに出没が多いのか」を整理する必要がある。
① 個体数の増加
北海道のヒグマ本体数は長期的に増加し、本州のツキノワグマも東北・中部・中国地方を中心に増加傾向が続いている。狩猟者の減少、保護政策の進展、温暖化による餌資源の変化などが背景にある。
② 人里環境の変化
放置された果樹、空き家、放任農地、生ゴミ問題など、人間側の“誘因物”が増えた。また、人口減少により山間部の人手が減り、かつてクマが避けていた集落周辺まで利用されるようになった。
③ クマの「学習」が急速に進んだ
一度ゴミや農作物で成功体験を得たクマは、非常に強く記憶し、人を恐れない個体(=人慣れ個体)として人里へ戻るようになる。
これがニュースで見る「街を歩くクマ」「昼間に徘徊するクマ」の正体に近い。
④ 気候変動
ドングリ・ブナの結実周期が変化し、不作の年にクマが餌を求めて広範囲へ移動することが増えた。
また、温暖化で冬眠が短くなり、活動期間が延びた地域もある。
こうした要因が複合し、“クマの増加”ではなく
「クマの行動圏が人間側へ広がった」
という状況が生まれている。
■ 世界のクマ管理:欧米は「保護」と「管理」を明確に分けている
他国の例を見ると、日本とは大きな違いがある。
海外、とくに北米やヨーロッパでは、クマの管理は「科学」「統計」「社会合意」に基づいて行われている。
● 北米(アラスカ・カナダ)
- クマの分布や個体数を毎年調査
- 「地域ごとの適正密度」を設定
- これを超えるとハンティング枠(収獲枠)を拡大
- 超えない場合は縮小または禁止
つまり、**数値で管理する“個体数モデル”**が確立している。
● スウェーデン・ノルウェー
- ブラウンベア(ヒグマと近縁)の“年間捕獲上限数”を政府が発表
- 住民の安全と生態系の両方を考慮し、
「北部は保護優先」「南部の農村地帯では管理優先」とゾーニングしている
これにより、
「基本は保護。ただし人の生活圏は守る」
というメリハリが実現している。
■ 世界の最新トレンド:「ゼロ距離を避ける管理」
野生動物全般の国際トレンドは明確だ。
“人と野生動物の距離がゼロに近づいた瞬間に衝突が起きる”
——だから、物理的・心理的な距離を意図的に“広げる”のが管理の基礎。
手法としては:
- 人里の生ゴミ管理の徹底
- 果樹や誘因物の撤去
- 電気柵や緩衝帯(バッファゾーン)整備
- 人里に近い個体の早期駆除(特に春)
- クマに「人間は怖い」と学習させる(威嚇・追い払い)
これらはすべて
“距離を保つための科学的手段”
として扱われている。
■ 日本がこれから取るべき「現実的なクマ対策」
日本の議論には
- 「クマがかわいそう」
- 「人命を守れ」
という両極がぶつかりがちだが、
実際には以下のような“中間的かつ現実的な政策”が国際的に推奨されている。
① ゾーニングを明確にする
- 山奥は保護エリア
- 人里の3km圏は管理エリア
- 農地周辺は厳格なノー・ベアゾーン
こうした空間管理を行うことで、捕獲の基準も明確になり社会的合意が生まれやすい。
② 春期管理捕獲の強化
冬眠明けの個体は行動が予測しやすく、人里に向かう前に除去できる。
これは欧米でも“最も効果的な予防策”とされている。
③ 若い個体(1〜3歳)の監視強化
若グマは行動圏が定まらず人里へ迷い込みやすい。
若齢個体を重点的に見つけ、追い払い・捕獲の対象にすると効果的。
④ 誘因物管理の徹底
- 空き家の放置果樹
- 放任された柿の木
- 生ゴミ・コンポスト
- 畑の残渣
これらを放置する限り、クマは必ず出没する。
これは“人間側の責任でできる対策”であり、最も費用対効果が高い。
⑤ 教育・啓発
海外では、
「野生動物問題は“住民教育”の問題」
と言い切られるほど、人間側の行動の影響が大きい。
- ゴミ管理
- クマに近づかない
- 見かけたら通報
- ペットの餌管理
- 山菜採りでの注意
こうした教育を、学校・自治体単位で進める必要がある。
⑥ 駆除は“最後の手段”として、透明性の高い基準で
駆除が感情論で論じられるのは、基準が曖昧なせいだ。
- 「人里1km以内に何回出没したら捕獲対象」
- 「昼間に人を恐れず行動した場合は捕獲」
- 「農地被害が一定水準を超えたら捕獲」
など、明確なルールを公にすれば、
社会の理解は飛躍的に高まる。
■ 動物愛護の視点と“命を守る管理”は矛盾しない
多くの人が誤解しているが、
動物愛護=捕獲反対
ではない。
欧米の動物福祉団体は、こう定義する。
「人間も野生動物も命を守るために、
ときに捕獲は必要な“管理行為”である」
ポイントは、
- 苦痛を最小化する
- 不要な捕獲をしない
- 子連れのメスは極力避ける
- 個体群全体に影響を与えないよう調整する
- 科学的根拠に基づく
という “倫理的な管理” を行うことだ。
日本でもこの視点を導入すれば、
「駆除=悪」「保護=善」という単純な対立から脱却できる。
■ 最終章:人とクマの“ちょうどいい距離”を社会で決める時代へ
クマ問題の本質は、
クマが増えたことでも、人間が悪いことでもない。
最大の問題は、
「人とクマの距離がゼロに近づいたこと」
だ。
かつて存在した里山のクッション、
人間の生活圏のにぎわい、
山と村を隔てていた空間――
これらが失われた結果、
日本は“クマと人が混ざり合う空間”を生み出してしまった。
だからこそ、これから必要なのは
距離をつくる政策
である。
- ゾーニング
- 春期管理捕獲
- 誘因物管理
- 住民教育
- 個体数の科学的管理
- 判断基準の透明化
これらが組み合わされば、
「人の命」と「クマの命」を両立させる社会は十分につくれる。
そして最後に明確にしておきたいのは、
日本はすでに“クマがいない国”ではなく、
これからもクマと共に生きる国だということだ。
だからこそ必要なのは、
敵か味方かではなく、
互いが安全に生きられる“距離感”を社会全体で決めていくこと。
それが、これからの日本のクマ対策の核心であり、
人間と自然の新しい関係を築く第一歩となる。